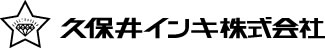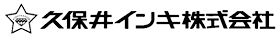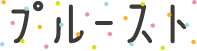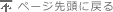スタッフブログ
スタッフブログ


バルーンアート
 2018年07月13日 | 個別ページ
2018年07月13日 | 個別ページこんにちは、製造部の勝です。
我が社では、毎年7月後半の土曜日に、「家族会」が開かれます。
普段一緒に働いている社員のご家族をお招きして、駐車場でBBQ をしたりします。
今年も開催予定で、幹事の人たちが準備に掛かっているようです。
自分は今年、幹事ではないですが、一年に一度のことなので、参加されるご家族の方々には楽しんでいただけたらなと思っています。
そんなわけで、今年も独自に動いていこうと、数年前に幹事をした時にやったバルーンアートを、久々にやってみたいと思います。
前回は作れる種類も少なく、クオリティも低かったので、少し練習しておきます。
これは今回初めて作ったものです。
小さい花は腕輪になっているので、女の子とかに喜ばれそうです。
これは定番の犬、サーベルです。男の子向けです。
まだまだ出来が甘いですが、当日はお子様たちの要望に応えられるように練習しておきます。
ただ、作れば作るほど、部屋の中がバルーンだらけのファンシーな部屋になります。
しばらくはバルーンに囲まれて寝ることになりそうです(笑笑)
久保井インキ株式会社
製造部 勝
ひむれのや
 2018年07月12日 | 個別ページ
2018年07月12日 | 個別ページ6月に長女が誕生日を迎えるので、「私もお父さんと同じようにバースデーケーキを作ってもらいたい!」と言われたので、またまた近江八幡市へ。
バースデーケーキをオーダーし、引き取り時間迄はかなりあります。近江八幡市の隣町に有る三井アウトレットパーク滋賀竜王でショッピングと昼食を済ませて早目に近江八幡市宮内町へ到着。
しかし今日は暑い。次女のワガママな一言「イチゴのかき氷が食べたい!」、まだ引き取り時間迄余裕があるので、和菓子でも買おうと言って、たねや日牟禮の舎(ひむれのや)の前に行くと氷の文字が目に飛び込んで来ました。
暑くなると無性に冷た〜い物が食べたくなるのは私も子供達もいっしょ。店内に入ると正面で職人さんが、つぶら餅タコ焼きみたいな餡子の入った丸い餅を焼いているのを見ながら併設の茶屋へ。囲炉裏と竃の有る店内でつぶら氷を注文し待ちました。
子供たちは、つぶら氷イチゴ。
これ、食べても舌が真っ赤にならないしイチゴの果肉がふんだんに使用されてるんですよ!!
私は黒蜜を注文しました。
食べる直前に煎りたてのきな粉を自分ですり潰してかけて食べます。きな粉の香りと黒蜜のかき氷に更につぶら餅と風味豊かな小豆茶を頂きリラックス出来ました。
尚、つぶら餅は日牟禮の舎限定ですが、かき氷は阪急うめだ本店地下のたねや茶屋で召し上がれますよ。興味のある方は行ってみてはいかがですか?
久保井インキ株式会社
製造部 奈良県民S
優勝国が決まるまで
 2018年07月11日 | 個別ページ
2018年07月11日 | 個別ページロシアワールドカップが開催されていますね。
普段はサッカーの試合はあまり観ず、野球中継を観る事が多いのですが、今の時期だけは放送されている試合を深夜早朝以外はほぼ観戦しています。
日本はコロンビアとの試合を序盤からの数的優位という大きなアドバンテージを得て初戦白星スタートをきることができました。
今回のワールドカップは強豪国といわれるチームが初戦から苦戦を強いられるスタートとなったり、開催国であるロシアが勢いを持っていたりと、面白い展開となっていると思います。それだけワールドカップという大会が何が起こるのかわからない厳しい大会なんだということを思い知らされます。
日本は惜しくもベスト8の壁を越えられませんでしたが、優勝国が決まるまでこのお祭り全体を楽しみたいと思います。
久保井インキ株式会社
製造部 かわちー
「本物のインドカレー」青ヒゲ食ブログ_その5
 2018年07月10日 | 個別ページ
2018年07月10日 | 個別ページ青ヒゲです。今回も美味しい食べ物をハンティングして行きたいと思います。
カレーといえば、インド料理。
最近では、インド料理屋のお店も増え、インド料理屋のカレーを食べたことのある方も多いのではないでしょうか?
インド料理屋のカレーのおいしさは日本のカレーのおいしさとはちょっと違うような気がして、個人的にもかなり好きです。
というわけで今日は、地元の有名店にインドカレーを食べに行きます!
場所:兵庫県西宮市
お店:サガルマータナマステ
メニュー:サガルマータセット
今回はチキンカレー(中辛)を選択。
辛いのが苦手な私は店員さんに、中辛で大丈夫そうですか?とお伺いしたところ、見事なサムズアップと笑顔で「大丈夫です」と言われたので、中辛にしました。
まずはナンから。焼き立ての生地を千切って食べてみます。
バターの風味がふんわりと口の中に広がっていき、とても美味しいです。
続いてカレーだけで一口頂きます。
最初は甘さの中で、後に少しピリっとするスパイス。中辛でこれなら大丈夫ですね。小学生のお子さんでも食べられるくらいかと思います。
カレーは野菜を細かく切って、煮込んでいる内に溶け込んだのか、口に残る旨味は野菜なのかな?そして、大きなゴロゴロチキンが4、5個入っていて、とても美味しい。
そういえば以前、弊社にもカレーの匂いのする香料インキを試作していましたが、あれはどうなったのだろうか。食べ物シリーズの香り印刷よ! もっと増えて欲しいですね。
総合的に、とても満足のいく味でした。ご馳走様です!
自宅近くなので、また来たいと思います。
久保井インキ株式会社
製造部「青ヒゲ」
似顔絵
 2018年07月09日 | 個別ページ
2018年07月09日 | 個別ページお初天神
 2018年07月06日 | 個別ページ
2018年07月06日 | 個別ページ一年ぶりに、お初天神に行く機会に恵まれました。
正式名称は「露天神社」。でも、お初天神が有名すぎて、誰も正式名称なんて知らないみたい。
昨年よりも人(参拝客)が多い感じ。外国語は聞こえてきません。さすがに神社。静謐な雰囲気は保たれているようです。
近松門左衛門の浄瑠璃「曽根崎心中」の看板?が目を引きます。
沢山の「絵馬」。恋の成就が多いのかな。(個人情報です。しっかりとは読んでいません。)
悲恋物語の神社で恋の成就を願うとは、これ如何に。なんて野暮なことを考えてのひと時でした。
梅田のど真ん中です。おいしい食べ物屋も沢山あります。
行かれたことのない方は、一度いかがでしょう。
久保井インキ株式会社
管理部 K
去りゆく恒例行事
 2018年07月05日 | 個別ページ
2018年07月05日 | 個別ページここ最近、家族で出かけたり、近くに住む親戚が集まったりする行事が年々減っているなぁと感じます。
今年は毎年恒例の潮干狩りに行きませんでした。
計画はしていたのですが、天気やら潮の具合でなかなか日程が合わず、結果的に行けなくなったのです。
昔は、しょっちゅう皆でご飯を食べたり、バーベキューをしたりしていましたが、近ごろは盆正月ぐらいしか集まることもなくなりました。
泊まりで行っていた海水浴も、ついに今年は白紙に。。。
その季節ごとにしかできない遊びや場所もあると思うので、皆と色んな所へ行きたいとは思うのですが、今後、気持ちとは裏腹にお流れになっていってしまうことが多くなりそうです。
それぞれの家族にそれぞれの変化があり、歳月の経過とともに変わっていくのは当たり前のことなのですが、なんだか寂しさも伴うものですね……
ですが、家族で出かけることが減った寂しさを埋めるべく(?)、なかなか会えなかった友達と会う機会が、去年あたりから増えています!
やはり、家にじっとしてはいられません!! この夏も満喫したいと思います。
久保井インキ株式会社
業務部 A
朝ドラ効果
 2018年07月04日 | 個別ページ
2018年07月04日 | 個別ページ今、ハマっているドラマがあります。
NHKの連続テレビ小説、「半分、青い。」です。
朝8時からとお昼に再放送で、1日に2回放送しているんですが、朝は見れないので、お昼のほうを見ています。
岐阜県の小さな田舎町で育った女の子が大人になり成長していくストーリーなのですが、そのドラマに出てくる、五平餅という郷土料理があります。
お米をつぶしたものを串に巻いて、タレをつけて焼いたお餅で、いつか食べてみたいなぁ~と思っていました。
すると先日の仕事帰り、たまたまいつもと違う改札の入り口を入ったところ、期間限定で、五平餅が売られていたのです。これも朝ドラ効果なのかなぁと、勝手に思っているうちに、私はお店へと並んでいました。
家に帰ってから食べてみたんですが、甘辛い味噌ダレの味でとても美味しかったです。
またどこかで出会えたら、食べたいですね。
久保井インキ株式会社
業務部 T
抹茶
 2018年07月03日 | 個別ページ
2018年07月03日 | 個別ページ先日大好きな抹茶のスイーツビュッフェに行って参りました(^^)
前日からワクワクしており、当日は駅から現地まで送迎バスで向かったのですが、バスの車内でも早く着かないかと期待に胸を膨らませておりました。
お店に着いてからは目の前が好きなものだらけでキラキラして眩しかったです!
きっと私ニコニコではなくニヤニヤしていたはずです…(笑)
何から取ればいいか迷ってしまうぐらい種類も豊富で少量ずつ取ったのですが、種類が多かったせいかすぐにお腹がいっぱいになってしまい、胃袋が3つあればと切実に思いました^^;
軽食も沢山用意されておりどれもとても美味しかったです(^^)
スイーツのディスプレイの仕方もすごく綺麗で見惚れていました。
スタッフさんの気配りも至るところまで行き届いており、素晴らしい時間を過ごせました(^^)/
頻繁にはできませんが、気分転換やモチベーション保持のためにもたまに贅沢もいいものですね!
次は何を食べようかと日々考えております( ̄▽ ̄)
久保井インキ株式会社
業務部 I
オクトーバーフェスト
 2018年07月02日 | 個別ページ
2018年07月02日 | 個別ページ今月の初めに、オクトーバーフェストに行ってきました!
オクトーバーフェストとはドイツのビール祭りの事で、ドイツビールを飲むだけではなく、食べ物や音楽も楽しみながらドイツ文化に触れよう、というイベントです。
当日は雨の心配もあったのですが、晴天に恵まれて暑いくらいでした。
ビールは苦手なので、まずは飲みやすそうな氷結柑橘ビールを選びました。
グラスいっぱいに柑橘類が入っていてさっぱりとした味で、飲みやすかったです!
一緒にソーセージやジャーマンポテトも食べたのですが、これまたビールがすすむのです!!
2杯目にクランべリービールを飲んでいると、ドイツ民謡の演奏が始まり、楽しくまたまたビールがすすみ、意外とドイツの食べ物が自分に合っている事にびっくりしました。
昔は地方や海外の料理や文化に触れる為には、その地に行かなければなりませんでしたが、今ではこういったイベントや百貨店での物産展なんかも頻繁に行われます。
こういった催しを通して、他の地域や国の文化や問題に目を向け、少しでも視野を広げるきっかけになればなぁと思いました(^^)
久保井インキ株式会社
業務部 T